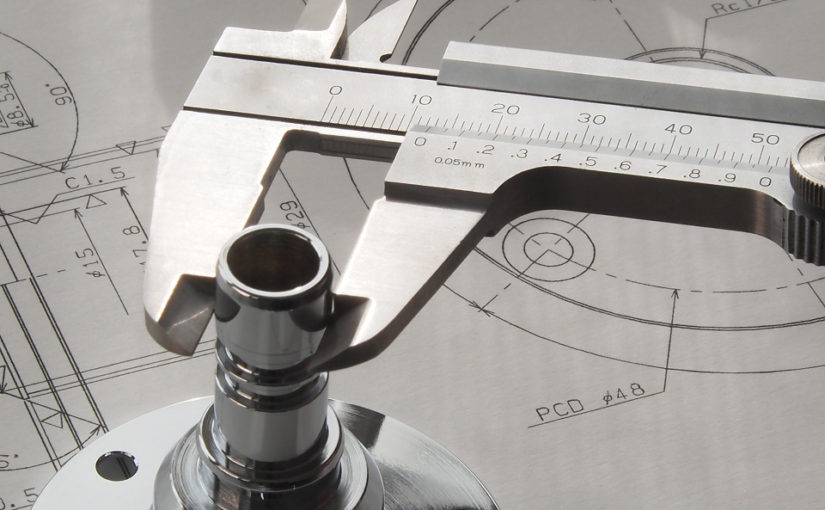業績を上げろと部員を締め上げる技術部長。そして技術部にはもうひとり、困った人がいるという。
■08-困った二人
「まずは大久保さんの話だ」越谷が続ける。
技術部長の大久保は生え抜きの技術部員だ。半年前、先代の社長の時代に部長に抜擢されたが、たいして技術的な実績のない大久保がなぜ部長? というひそかな声があがっていた。
「なんでも業績ばかり追いかけて、ライバルのことも気にして、それで現場を混乱させた。そうだな川口くん」
「ええ。決算の2週間前に、『もっと数字がよくならないのか』とか言いだすんです。開発や製造で巻き返すことなんて不可能な時期にですよ」
「それは粉飾決算しろということだぞ」
「さすがに技術部ではそんな数値操作はできないとつっぱねましたが。もちろん経理部でも、です」
◆大物登場
「そんなことがあったのか…。それでもうひとり、違う形で困った人とは?」
「はい。ほかでもない製作本部長です」
川口は、ちょっと思いつめた表情で訴えた。
「おいおい、大久保部長も、その上の高円寺本部長も、両方問題ありってことか」
製作本部長は技術部、製造部、品質管理部の三部を統括する。半年ほど前、これも先代社長の政権末期に就任した高円寺は、一部上場メーカーの管理畑からの転籍者だ。
目黒は半年前、つまり高円寺が当社にやってきたころに技術部から製造部に移った。いずれにしても高円寺は上司筋に当たるのだが、ルーティンワークの多い製造部ではあまりその影響力が及ぶことはなく、彼がどんな人物なのかもよく知らなかった。
「で、高円寺さんがなんだって」
「仕事をさせてくれないんです」
「え?」
そこへ川口の携帯で着信音が鳴った。
「うん、いま監査部だ。…あ、船橋さん、すこしこっちへ来ないか」
◆仕事をさせない上司
ノックの音がして、扉の間から若い女性の顔がのぞいた。
技術スタッフ用のグレイのジャケットに、自前のものらしい濃紅色のリボンと白いブラウスをのぞかせている。知的な顔立ちに、力強い視線が印象的だ。その目元がやわらかい弓形に変わり、笑みがこぼれた。
「こんにちは、船橋理央です」
玉川あけみとは顔見知りらしく、さかんにアイコンタクトを送りあっている。
「船橋さん、さっそくだけどきみたちのボツ企画について話してくれないか」
川口が切り出す。
なんとなく話の内容を察したのか、あらたまった顔の越谷が注釈を入れる。
「船橋さん、でしたな。わたしたちには守秘義務があります。調査権も、閲覧権も聴聞権もある」
すこし棒読み口調だし、聞いただけではなんの話かよくわからない。
「だからなんでも包み隠さず、話してみてください」
船橋理央は、会釈すると話し始めた。
◆企画が通らない
「当社が企画優位の会社だということはみなさんご存じでしょう」
当社、すなわち千堂工学には消費者向けの商品がない。業務用の機器や機能部品、それに少量生産の高機能素材を作っている、いわゆるBtoBのメーカーだ。大発明というわけではないが、あまり市場になかった種類の製品を企画し、すばやく製品化して供給することを得意としている。
「3つの開発チームがあって、競い合うようにして企画を打ち出していました。合同の飲み会をよく開くような、いいライバル関係なんですよ。それはいまでも続いています。だけど…」
船橋はすこし顔を曇らせて息をついだ。
「企画が通らなくなったんです。『各社のノズルを他社のベースボードに固定できるポリカーボネート台座』はだめ。『エンベッド用の超小型熱交換部品』もだめ。『多重ピッチの部品実装ができる汎用アセンブリ基板』もだめ」
◆いくら儲かるんだ
上野の目が宙を泳いだ。営業として自分が担当した製品ならわかるが、まだ企画段階のものについてはイメージしにくいらしい。
越谷もほとんど労務や総務で過ごしてきて、いまの話が理解できるとは思われないが、そこは年の功か、落ち着きはらっている。
「なぜその、企画が通らなくなったのだろうか」
「企画が上がっていって、本部長のところまでいくと、そこでつぶれるんです。『製品はいつできあがるのか。企画どおりに売れるのか。いくら儲かるんだ。欠陥品でクレームがついたりしないだろうな』などと言って」
川口がつけ加える。「本部長の企画承認を取ったら、技術的な検証もするし、マーケティング調査もします。だけどその前に、『準備が足りていないようだな』みたいな話になってダメが出るんです」
「しかたがないので検証に着手してから持っていくようにしたんですが、それでもいろんな理由をつけてダメ。たとえば『もっと儲かる話を持ってこい』とか『こいつはクレームがこわいな』とか」
◆オレに責任が来る
「そのクレームの話がまた、たいへんで」川口が引き継ぐ。
「目黒さんも安全第一ですが、それとは違うんです。高円寺さんの言い方は『こいつが事故でも起こしてみろ。会社の評判は悪くなるし、賠償金や訴訟費用がかかるし、結局のところ責任がオレに来ちゃうんだよ』になってしまう。
目黒さんみたいに『最終消費者のお客さまがケガしたところを想像してみろ』のようなことは言わない。『オレに責任が来るんだ』ばかりで、お客さまのことが眼に入っていないみたいです」
「アウトオブ眼中、ってやつか」と上野。
「おかしいでしょう、こんなことって。わたしも川口さんも、ものづくりが好きで、それを長いあいだ勉強して、会社に入ったんです。でもなにも作らせてもらえない」
◆つるつるの壁
目黒は、社歴のほとんどを過ごしてきた製品開発の現場を、まさに昨日のことのように思い起こしていた。
つるつるの壁をよじ登るような苦しさで、なにもないところから課題を見つけ出す。解決策を構想する。具体的なモノが形づくられていく。試作品が思ったとおりに動いたときの喜び。
テストマーケティングで顧客に見せて、こっぴどく叩かれる。チームの知恵を集めて工夫する。そうして仕上がったモノを製造にかけ、出荷するときの喜び。
エンジニアが味わったそんな苦楽を背に、製品は世に出て役に立つ。会社も潤う。それが支えでこれまでやってきた。
そんな過程が、途中で断ち切られたらどうだろう。苦労だけが残ってなにも報われなかったら、どんな気持ちになるか。断ち切るのに正当な理由があれば文句はないのだが。
「越谷さん、これは大問題のようですね」
冷静を売りにしているはずが、すこし声がかすれた。
(天生臨平)